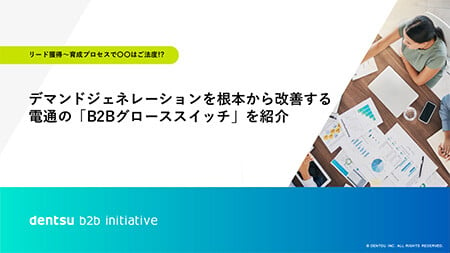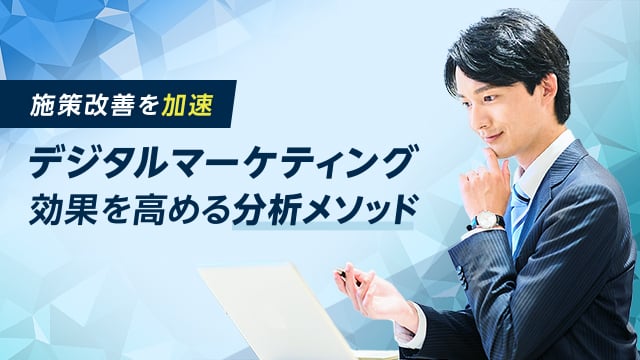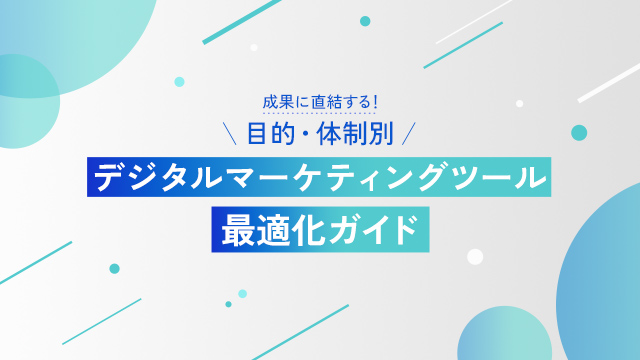デジタルマーケティングは、データと技術を駆使して見込み客との信頼関係を構築し、商談創出から受注まで一貫した顧客体験を設計する戦略的手法です。近年のトレンドとして、 AI主導のパーソナライゼーションやデータドリブン戦略が注目を集めています。
特にBtoB企業においては、これらのトレンドを効果的に取り入れることで、競争力を維持し、成長を続けることが可能です。
本記事では、これらの最新トレンドをもとに、BtoB企業が優先すべきデジタルマーケティング戦略のポイントと、顧客との関係強化や市場での優位性を確立する方法を探ります。
INDEX
デジタルマーケティングの最新トレンド一覧
デジタルマーケティングの世界は急速に進化しており、最新のトレンドを把握することが成功への鍵です。ここでは、業界で注目されている最新のデジタルマーケティングトレンドを一覧にしてご紹介します。
-
生成AIによるマーケティング業務の自動化と最適化
-
顧客体験を高めるパーソナライズの進化と実例
-
ゼロパーティデータが注目される理由
-
マーケティングオートメーション(MA)との掛け合わせで広がる可能性
-
AI×クリエイティブによるデータドリブンと感性の融合
生成AIによるマーケティング業務の自動化と最適化
生成AIは、マーケティング業務の自動化と最適化において重要な役割を果たすツールです。現在では、AIが自然言語処理を活用して高品質なブログ記事やソーシャルメディア投稿を自動生成するツールが数多く提供されています。
BtoBの分野においても、AIを用いて顧客の業種や課題に応じたカスタマイズされたコンテンツを生成し、リードナーチャリングの効率化に寄与する事例が増加しています。例えば、特定の業界に特化したホワイトペーパーやケーススタディを効率的に作成することで、営業チームがより効果的に見込み客にアプローチできるようになります。
さらに、AIを活用したスコアリングとリード評価の高度化も、注目の活用方法です。リードスコアリングにAIを用いることで、ホットリードをより正確に特定し、営業チームが重要なリードに集中できるようになります。
AIは膨大なデータを分析し、行動パターンや関心領域を把握することで、従来の手法よりも精度の高いリード評価が可能です。
顧客体験を高めるパーソナライズの進化と実例
消費者はより個別化された体験を求めており、企業はこれを提供することで顧客満足度を高めています。
最新のトレンドとしては、AIと機械学習を活用したリアルタイムのデータ分析により、瞬時にパーソナライズされた体験を提供する技術が注目。
BtoBの領域では、購買履歴や行動データをもとにしたターゲティング広告やパーソナライズされたメールキャンペーンが特に重要です。これにより、企業は特定の業種や規模に合わせた提案を行うことができ、商談の成功率を向上させます。
ゼロパーティデータが注目される理由

ユーザーから直接提供されるゼロパーティデータは信頼性が高く、プライバシーにも優れています。最近では、プライバシー規制が厳しくなる中で、ゼロパーティデータを活用したマーケティングがさらに重視されています。
BtoBでは、顧客企業が自発的に提供するデータを活用し、カスタマイズされたソリューションを提案することで、より強固なパートナーシップを構築。このデータを活用して、より正確で効果的なマーケティング施策を展開できます。
マーケティングオートメーション(MA)との掛け合わせで広がる可能性
MAツールとの組み合わせにより、企業はリードジェネレーションから育成、顧客維持までのプロセスを自動化し、効率を向上させています。
最新のトレンドとしては、AIを活用した高度な予測分析を取り入れ、見込み客の行動を予測して最適なタイミングでのアプローチを可能にするオートメーションツールが増加。
BtoBでは、セールスチームとマーケティングチームの連携を強化し、見込み客を適切なタイミングでフォローする仕組みを構築することが重要です。
AI×クリエイティブによるデータドリブンと感性の融合
データドリブンなアプローチとクリエイティブな感性を組み合わせることで、顧客の心に響くメッセージを届けることが可能です。
最近では、AIがクリエイティブのプロセスにおいても大きな役割を果たし、例えば自動でバナー広告をデザインしたり、動画コンテンツを編集したりするツールが登場しています。
BtoB企業は、顧客の業種や特性に応じたクリエイティブなキャンペーンを展開し、他社との差別化を図ることができます。
デジタルマーケティングの基本情報はこちらをご参考ください。
【5分でわかる】デジタルマーケティングとは?基本と実施プロセス&手法一覧、成功事例を紹介
デジタルマーケティングに関連する規制対応などの環境変化トレンド
デジタルマーケティングのトレンドはポジティブなものだけでなく、規制などの環境変化もさまざま見られます。
デジタル領域における法規制環境の変化背景

デジタルマーケティングの規制環境が急速に変化している背景には、テクノロジーの進化と共に増加するデータ利用への懸念があります。インターネットの普及に伴い、企業は膨大なユーザーデータを収集し、マーケティング戦略に活用してきました。
しかし、これに伴いプライバシー侵害やデータ漏洩のリスクが高まり、消費者のデータ保護意識が強まっています。このような状況を受け、各国は個人情報の保護を強化する法規制を整備するようになりました。
海外では情報の不正利用防止の観点で厳しい規制を展開
例えば、EUのGDPR(一般データ保護規則)や米国のCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)は、企業がどのようにデータを収集・使用するかを厳しく規制し、消費者に対する透明性とコントロールを提供。これらの法規制は、消費者の信頼を確保し、情報の不正利用を防ぐことを目的としています。
デジタル規制の中で生まれる、ユーザーに配慮したデータ活用のアプローチ
このような規制の中で、各企業はデータ収集方法を見直し、よりユーザー中心のアプローチを模索しています。
具体的には、Google Analytics 4(GA4)の導入や、Googleが一度発表したサードパーティCookie廃止計画(2024年7月に撤回されたものの、Privacy Sandboxなどの代替技術開発は継続)がその一環であり、これによりユーザーのプライバシーを尊重しつつ、よりパーソナライズされた体験を提供するために、ファーストパーティデータやゼロパーティデータの活用が進んでいます。
さらに、クッキー規制強化の流れの中で、Googleの「Privacy Sandbox」や大手プラットフォームとの「データクリーンルーム」連携が注目。これらの技術は、個人情報を保護しながらも、広告効果を最大化するための新たな手法として期待されています。
Privacy Sandboxは、より安全な広告ターゲティングを可能にし、データクリーンルームは企業が他社と安全にデータを共有し、分析を行うための環境を提供します。
プライバシー保護とユーザー体験のバランスを取るためには、透明性のあるコミュニケーションと、ユーザーの同意を得るプロセスが重要です。企業は、データの利用目的を明確にし、ユーザーに対して選択肢を提供することで、より信頼性の高い関係を築くことが求められます。
この透明性と信頼構築は、デジタルマーケティングの成功に寄与するでしょう。プライバシー保護とユーザー体験のバランスを整理した表が以下になります。
|
視点
|
ユーザーにとっての期待
|
企業に求められる対応
|
結果としての信頼構築の要素
|
| プライバシー | 自分のデータが勝手に使われないこと | データ利用目的の明示と同意取得 | 透明性・選択肢提供 |
| 体験 | 自分に合った提案や情報が届くこと | ファースト/ゼロパーティデータの活用 | パーソナライズと信頼の両立 |
| コントロール | いつでも設定を変えられること | オプトイン/アウトの容易なインターフェース設計 | 継続的なコミュニケーション |
日本においても法改正により適切なデータ管理対応が求められている

さらに、日本や海外で進む法規制の最新動向として、日本では個人情報保護法が改正され、海外ではデータ保護規制がさらに厳格化しています。これにより、企業は国際的な規制に適応するための実務的な対応が求められるでしょう。
例えば、データの越境移転に関する手続きや、各国の個別規制に対応したデータ管理体制の構築が必要です。
このように、規制対応は単なる法律順守に留まらず、企業の信頼性を高め、ブランド価値を向上させるための重要な戦略となっています。デジタルマーケティングの最新トレンドを理解し、迅速に適応することが、現代のマーケティング成功への鍵です。
こうした変化を捉え、積極的に対応することが、企業の競争力を維持・向上させるための重要な要素となっています。
わたしたち電通B2Bイニシアティブでは、BtoB事業活動全般の戦略立案はもちろんのこと、デジタル領域の知見を活用した具体的な施策の実行から最終的な成果を分析・改善し続けるためのサイクルの創出まで伴走支援が可能です。
支援の詳細については、以下をご覧ください。
デジタルマーケティングにおけるコンテンツ形式のトレンド進化を追う
デジタルマーケティングの領域は、技術革新と消費者行動の変化によって日々進化を遂げています。企業が競争力を維持するためには、最新のトレンドを把握し、それに応じた戦略を構築することが不可欠です。
ここからは、デジタルマーケティングにおける新しいコンテンツ活用の可能性や重要なポイントに焦点を当て、企業の成長にどのように活かせるかを探っていきます。
検討初期の関心を引くショート動画のBtoB活用法
デジタルマーケティングの世界では、コンテンツ形式の進化が顕著であり、特にBtoB企業においてもこの変化を捉えることが重要です。
2024年頃から見られる最新トレンドとして、従来のテキストや静止画中心の情報発信から、動画コンテンツへのシフトが加速しています。中でもショート動画は、検討初期の顧客の関心を引く注目の手法です。
ショート動画は短時間で要点を伝えられるため、忙しいビジネスパーソンに適しています。製品やサービスの特徴を簡潔に説明し、視覚的に訴求することで、初期段階の認知拡大と興味喚起に効果的です。
さらに、SNSや企業のウェブサイト、メールマーケティングなど多様なチャネルでの活用が可能であり、複数の接点で顧客とのエンゲージメントを高めます。
ショート動画を活用した効果最大化のポイントは以下となります。
-
コンパクトでわかりやすいメッセージ設計
-
視覚的な魅力を重視したクリエイティブ制作
-
ターゲットの課題や関心に直結した内容
-
多チャネルでの一貫した展開
-
視聴データの分析による効果測定と改善
これらのポイントを踏まえ、BtoB企業はデジタルマーケティング戦略にショート動画を組み込むことで、従来の広告手法よりも高い効果を実現できるでしょう。動画の活用は単なる情報提供にとどまらず、顧客との信頼関係構築やブランド価値向上にも寄与します。

今後も動画を中心としたコンテンツ形式の進化は続く見込みであり、BtoB企業が競争力を維持・強化するためには、このトレンドをいち早く取り入れることが不可欠です。
デジタルマーケティングの最新動向を踏まえ、適切な動画活用手法を実践することで、効果的な顧客アプローチを実現しましょう。
顧客事例を「見せる」時代へ、動画インタビューと導入事例の活用
デジタルマーケティングの最新トレンドの一つとして、顧客事例を動画で「見せる」手法がBtoB企業で注目されています。従来のテキスト中心の事例紹介から進化し、動画インタビューや導入事例動画を活用することで、よりリアルで説得力のある情報提供が可能となりました。
動画は視覚と聴覚に訴えるため、顧客の成功体験や導入効果を直感的に伝えられ、信頼感の醸成やブランド価値の向上に寄与します。
|
活用ポイント
|
期待できる効果
|
| 実際の顧客の声を動画で届ける | 信頼性の向上と共感の獲得 |
| 導入前後の課題と解決策を具体的に示す | 課題解決力のアピール |
| 動画インタビューにより表情や感情を伝える | 感情的なつながりの強化 |
| 成功事例の具体的な成果を数値で示す | 説得力の増加と意思決定支援 |
| 顧客企業のブランドや業界特性を反映 | ターゲット層への訴求力強化 |
動画インタビューでは、顧客のリアルな声や導入効果を直接聞くことができるため、潜在顧客に対して具体的なイメージを持たせやすくなります。また、動画ならではの臨場感や信憑性が、商談の初期段階から顧客の信頼を獲得する重要な役割を果たすのです。
導入事例動画は、製品やサービスの効果を視覚的に示すことで、ビジネスの価値を直感的に理解させるため、BtoB企業のマーケティング戦略において欠かせない要素となっています。
こうした動画事例は、デジタルマーケティングの多様なチャネルで活用可能であり、ウェブサイトやSNS、メールマーケティングなどを通じて幅広く配信することで、顧客接点を増やし、効果的なエンゲージメントを実現します。
今後も動画による顧客事例の活用は、BtoB企業が競争優位を築くための重要なマーケティング手法として、さらに注目されるでしょう。
UGCのBtoB活用で、技術者や現場担当者の声をどう引き出すか?
デジタルマーケティングの最新トレンドの一つに、UGC(ユーザー生成コンテンツ)のBtoB活用があります。特に技術者や現場担当者の声を活用することで、製品やサービスの信頼性を高め、ブランド価値の向上につなげることが可能です。
UGCは従来の企業発信コンテンツとは異なり、リアルで説得力のある情報源として顧客からの共感を得やすい特徴があります。
技術者や現場担当者の声を引き出すには、以下のような具体的な方法があります。
|
方法
|
特徴
|
| インタビューや座談会の開催 | 直接対話により詳細な課題や成功体験を引き出す |
| 社内SNSや専用プラットフォームの活用 | 日常的な声を手軽に収集し、リアルタイムで共有可能 |
| アンケートやフィードバックフォームの設置 | 広範囲の意見を効率的に集める |
| 動画や写真の投稿促進 | 視覚的に訴求力のあるコンテンツを増やす |
これらの手法を組み合わせることで、多様な視点からのUGCを効果的に収集できるでしょう。特にBtoBでは、技術的な詳細や現場の具体的な課題解決事例が信頼性を高め、潜在顧客の関心を引きつけます。
UGC活用のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
|
メリット
|
詳細
|
| 信頼性の向上 | 第三者のリアルな声が企業の信頼感を強化 |
| ブランド価値の強化 | 現場の声を反映したコンテンツがブランドイメージを向上 |
| 顧客とのエンゲージメント促進 | 参加型の情報発信が顧客関係を深化 |
| マーケティング効果の向上 | 具体的な事例やフィードバックが購買意欲を刺激 |
ただし、UGC活用に際しては、情報の正確性やプライバシー保護、社内外の合意形成などの課題も存在。これらをクリアするためには、運用ルールの整備や投稿内容の適切な管理が必要です。
ウェビナー・ライブ配信が営業活動に進化
ウェビナーやライブ配信は、デジタルマーケティングの最新トレンドとして、BtoB企業の営業活動において重要な役割を果たしています。
従来の動画コンテンツとは異なり、リアルタイムでの双方向コミュニケーションが可能なため、顧客とのエンゲージメント強化や関係構築に大きな効果をもたらします。
ウェビナー・ライブ配信の主な特徴とメリットは以下の通りです。
|
メリット
|
特徴
|
| リアルタイムでの双方向コミュニケーション | 顧客の疑問や関心に即座に対応でき、信頼関係を構築しやすい |
| 場所や時間の制約を超えた参加が可能 | 地理的な制限がなく、多様な顧客層にリーチできる |
| 専門的な内容を深く掘り下げられる | 製品やサービスの詳細説明やデモンストレーションに適する |
| 参加者データの取得と分析が可能 | 見込み顧客の行動分析やフォローアップに活用できる |
営業活動における具体的な活用方法としては、以下のようなものがあります。
-
新製品やサービスの紹介セミナーとして活用し、直接質問を受けることで顧客理解を深める
-
既存顧客向けにアップセルやクロスセルの提案を行い、顧客満足度と売上向上を図る
-
業界トレンドや課題に関する専門的な情報提供を通じて、顧客の信頼を獲得する
-
営業チームとマーケティングチームが連携し、リードナーチャリングや商談促進に活用する
さらに、ウェビナー・ライブ配信による顧客エンゲージメント強化のポイントは、参加者との双方向コミュニケーションの促進にあります。質疑応答やチャット機能を活用して顧客の声をリアルタイムで拾い上げることで、ニーズに的確に応え、信頼感を高められるのです。

成功させるための注意点としては、技術トラブルの防止やコンテンツの質の確保、適切な告知とリマインド配信による参加率向上が挙げられます。また、配信後のフォローアップ体制を整え、得られたデータを活用して営業活動の改善につなげることも重要です。
これらのポイントを押さえ、ウェビナーやライブ配信を効果的に活用することで、BtoB企業は営業活動を進化させ、顧客との強固な関係構築と売上拡大を実現できます。
デジタルマーケティングの最新トレンドを踏まえた戦略的なライブ配信の活用は、今後ますます重要性を増していくでしょう。
複数チャネルに対応するBtoBコンテンツ設計のベストプラクティス
2024年以降のデジタルマーケティングにおいて、BtoB企業が成功を収めるためには、複数チャネルに対応したコンテンツ設計が欠かせないものとなってきています。
企業の顧客は多様な接点を通じて情報を取得するため、チャネルごとの特性を理解し、最適なコンテンツを設計することが重要です。
複数チャネル対応のコンテンツ設計では、以下のポイントが特に重要となります。
|
ポイント
|
具体的内容と効果
|
| チャネル特性の理解 | ウェブサイト、メール、SNS、ウェビナー、動画など、それぞれのチャネルの利用目的やユーザー行動の違いを把握し、適切なコンテンツ形式やメッセージを設計する |
| 一貫性の維持 | ブランドメッセージや価値提案をチャネル間で統一し、顧客に混乱を与えず信頼感を高める |
| 顧客ジャーニーに沿った最適化 | 顧客の購買フェーズ(認知、検討、決定)に応じて、各チャネルで最適なコンテンツを提供し、スムーズな購買プロセスを支援する |
| データ分析と改善サイクルの構築 | 各チャネルの効果測定を行い、顧客行動データを活用してコンテンツ戦略を継続的に改善する |
| チャネル間の連携強化 | CRMやMAツールと連携し、顧客データを統合管理することで、チャネル横断的なパーソナライズと効果的なフォローアップを実現する |
これらの実践的なポイントを踏まえ、BtoB企業は複数チャネルを効果的に活用し、顧客とのエンゲージメントを最大化できます。
特に、チャネルごとの特性に応じたコンテンツ設計は、顧客のニーズや行動にマッチした情報提供を可能にし、結果としてマーケティング効果の向上と売上増加に直結するでしょう。
さらに、チャネル間での一貫性を保つことで、ブランドの信頼性が高まり、競合他社との差別化にも貢献します。加えて、データドリブンな改善サイクルを確立することにより、変化する市場環境や顧客の行動変容に柔軟に対応できる体制を構築可能です。
総じて、複数チャネルに対応したBtoBコンテンツ設計は、今後のデジタルマーケティング戦略の中核をなす重要な要素です。企業はこれらのベストプラクティスを取り入れ、顧客体験の質を高めることで、持続的な成長を実現していくことが求められます。
静止画・PDF頼みから脱却し、動画を起点としたコンテンツ設計
デジタル時代において、企業は静止画やPDFといった従来のコンテンツ形式だけでは競争力を維持することが難しくなっています。特にBtoBマーケティングの領域では、情報の伝達力や訴求力を高めるために動画コンテンツの活用が急務となってきました。
動画は視覚的に訴える力が強く、複雑な情報を短時間で効果的に伝えることができるため、顧客の興味を引きつけやすく、エンゲージメントを高めるのに非常に有効です。

動画を起点としたコンテンツ設計では、まずターゲットのニーズを深く理解し、それに応じたストーリー性のある動画コンテンツを制作することが重要です。例えば、製品の特徴や導入事例を動画でわかりやすく示すことで、潜在顧客の購買意欲を高めることができます。
さらに、動画を基軸に他の形式のコンテンツを組み合わせることで、相乗効果を生み出すことも可能です。例えば、動画の要約をブログ記事にし、詳しい解説をPDF資料として提供することで、異なる情報取得の好みを持つ顧客に対応できます。
動画コンテンツを効果的に活用するためには、制作だけでなく、効果測定やフィードバックの収集、改善のサイクルを回すことも欠かせません。これにより、常に進化するマーケットのニーズに応え続ける柔軟なコンテンツ戦略を構築することができるのです。
BtoB領域のデジタルマーケティングでチャレンジしたい、新たなチャネル活用
デジタルマーケティングのトレンドはコンテンツだけでなく、チャネル活用の領域にも広がってきています。特に、LinkedInやウェビナーといったプラットフォームが注目されています。これらのチャネルを活用することで、ターゲット企業とのエンゲージメントを深めることが可能です。
また、マーケティングオートメーションツールを駆使して、見込み顧客の行動データを分析し、パーソナライズされたコンテンツを提供することが重要です。これにより、企業は従来の枠にとらわれない戦略を構築し、競争力を高めるチャンスを得られます。
LinkedIn活用の最前線
BtoB企業のデジタルマーケティングにおいて、LinkedInは採用活動からリード獲得まで多岐にわたる効果的なチャネルとして急速に注目を集めています。特に最新トレンドとして、LinkedInのビジネス向け機能を活用した戦略的な運用が成功の鍵です。
LinkedInは、プロフェッショナルが集まるSNSであり、高度なターゲティング機能を活かし、企業は効率的に潜在顧客や優秀な人材にリーチできます。採用面では、求人情報の掲載だけでなく、企業文化や働き方を発信することで、ブランド力を高め、優秀な人材の獲得につなげることが可能です。
一方で、マーケティング面では、リードジェネレーション広告やコンテンツマーケティングを通じて、質の高い見込み顧客の獲得を狙います。
以下に、LinkedIn活用の主要なポイントとその効果をまとめました。
|
活用ポイント
|
具体的内容
|
期待できる効果
|
| ターゲティング精度の高さ | 業種、役職、スキル、勤務地など細かく設定可能 | 潜在顧客や人材をピンポイントでアプローチできる |
| 企業ブランディング | 企業文化やビジョンを定期的に発信し、認知度アップ | 優秀な人材の採用力強化とブランド価値向上 |
| リードジェネレーション広告 | フォーム付き広告で効率的に見込み顧客情報を獲得 | 質の高いリードの獲得と営業支援の強化 |
| コンテンツマーケティング | 業界動向や事例紹介など価値ある情報を継続発信 | 顧客との信頼関係構築とエンゲージメント向上 |
| インサイト分析機能の活用 | 投稿や広告の効果測定と改善に役立つデータ取得 | マーケティング施策の最適化とROI向上 |
これらのポイントを踏まえ、LinkedInを活用したBtoBマーケティングは、採用からリード獲得、ブランド強化まで幅広い効果をもたらします。企業は戦略的なコンテンツ計画と精緻なターゲティングを組み合わせることで、デジタルマーケティングの最新トレンドに対応した効果的なチャネル運用を実現できるのです。
今後もLinkedInは、BtoB企業が競争優位を維持し、持続的な成長を遂げるために欠かせないチャネルとして、注目され続けるでしょう。
ポッドキャストがBtoB領域で注目され始めている
ポッドキャストは、近年BtoB領域のデジタルマーケティングにおいて注目される新たなチャネルです。音声コンテンツとしての特性を活かし、専門的な情報発信や業界知識の共有に適しているため、企業のブランド価値向上や顧客との信頼関係構築に効果的です。

日本では、ポッドキャストはまだそれほど普及していないものの、徐々にビジネスシーンでの活用が進んでいます。特に、ニッチな分野や専門性の高い業界では、ポッドキャストを通じて深い知識を提供することが顧客の信頼を得る手段として期待されています。
以下は、ポッドキャストがBtoBマーケティングにおいて効果的な理由とその具体的なメリットです
|
メリット
|
特徴
|
| 専門性の高いコンテンツ提供が可能 | 業界の深い知識や最新トレンドを詳しく解説し、ターゲット顧客の信頼を獲得できる |
| 通勤や作業中に聴取できる利便性 | 時間や場所を問わず情報収集が可能で、忙しいビジネスパーソンの生活にフィットする |
| 継続的な関係構築 | 定期配信により顧客との接点を増やし、ブランド認知とエンゲージメントを強化 |
| 他チャネルとの相乗効果 | 動画やSNS、メールマーケティングとの組み合わせで多面的なアプローチが可能 |
| コスト効率の良さ | 動画制作に比べ制作コストが抑えられ、継続的な情報発信がしやすい |
ポッドキャストは特に、技術的な解説や業界動向、顧客事例の深掘りなど、BtoB企業が伝えたい内容をじっくりと届けるのに適しています。例えば、専門家を招いたインタビューやパネルディスカッション形式での配信は、信頼性の高い情報提供として顧客から高く評価されるでしょう。
導入にあたっては、配信の継続性とコンテンツの質が成功の鍵となります。ターゲット顧客のニーズを的確に捉え、テーマ設定や配信頻度を計画的に行うことが重要です。
また、他のデジタルマーケティング施策と連携し、ポッドキャストの内容をSNSやメールで効果的に拡散する戦略も欠かせません。
ニッチな業界メディアとの連携と影響力の活用方法
BtoB領域のデジタルマーケティングにおいて、ニッチな業界メディアとの連携は、特定の専門分野に特化したターゲット層への効果的なリーチと影響力拡大に非常に有効な手法です。
大手メディアやSNSとは異なり、業界特有の課題や関心に深くアプローチできるため、質の高いリード獲得やブランド強化につながります。
ニッチな業界メディアの活用メリットと特徴を以下に整理してみました。
|
メリット
|
特徴
|
| 高い専門性と信頼性 | 業界に特化した情報発信により、ターゲットからの信頼を獲得しやすい |
| ターゲット層への精度の高いリーチ | 特定業界の意思決定者や担当者に直接的にアプローチ可能 |
| 競合との差別化 | 専門的なコンテンツでブランドの独自性を強調し、競合優位性を高める |
| コンテンツの多様な展開 | 記事、動画、ウェビナーなど多様な形式で情報発信が可能 |
| 長期的な関係構築 | 継続的な連携により業界内でのプレゼンスを高める |
そして具体的な連携方法としては、以下のような施策が効果的です。
-
共同記事や特集の企画・掲載:専門性の高いコンテンツを共に制作し、信頼性を担保する
-
広告やスポンサーシップの活用:業界メディアの広告枠を活用し、ターゲットに直接訴求
-
ウェビナーやオンラインイベントの共催:メディアのネットワークを活かして集客力を高める
-
インフルエンサーや専門家との連携:業界内のキーパーソンを巻き込み、影響力を拡大
-
ニュースレターやメールマガジンでの情報配信:定期的に専門情報を届けることでエンゲージメント向上
成功のポイントとしては、メディア選定の慎重さと連携内容の明確化が挙げられます。適切なメディアを選び、企業のターゲットや目的に合ったコンテンツや施策を計画することが重要です。
また、連携先とのコミュニケーションを密にし、双方の期待値を調整しながら運用していくことが成功の鍵となります。
BtoBでも求められるストーリーテリングとエモーショナルな訴求

BtoB領域のマーケティングにおいても、単なる製品やサービスの機能説明だけでなく、顧客の感情に響くストーリーテリングとエモーショナルな訴求がますます重要です。
実際にデジタルマーケティングのトレンドとして、顧客体験の質を高め、ブランド価値を強化するために、感情に訴えるコンテンツ制作が求められています。
ストーリーテリングは、情報を単に伝えるだけでなく、顧客の課題や成功体験を物語として描くことで、共感や信頼を獲得しやすくします。
特にBtoB領域では、意思決定者が理論的な判断と同時に感情的な納得も求める傾向があり、感情に響くメッセージが商談成立を後押しするケースも存在します。
|
訴求方法
|
具体例
|
期待できる効果
|
| 顧客の課題に焦点を当てる | 顧客が直面する具体的な問題やニーズを明確にし、それに対する解決策を物語る | 共感を呼び、顧客の関心を引きつける |
| 成功体験の共有 | 実際の事例や導入効果をストーリー化し、具体的な成果を示す | 信頼感の向上と説得力の強化 |
| ブランドの価値観・理念を織り込む | 企業のミッションやビジョンを物語に反映し、ブランドイメージを強化 | ブランドロイヤルティの醸成 |
| 感情を動かすメッセージ設計 | 顧客の感情に訴える表現や言葉選びを工夫し、印象に残る訴求を行う | 記憶に残りやすく、行動喚起に結びつく |
| 一貫したストーリー展開 | 複数のチャネルで一貫した物語を伝え、顧客体験を統合的に設計する | ブランドの信頼性向上と顧客エンゲージメントの強化 |
効果的なストーリーテリングの実践ポイントとしては、顧客の声や事例を積極的に取り入れ、リアルな体験を伝えることが重要です。また、感情に響くメッセージ作りには顧客のペインポイントを深掘りし、解決への希望や未来像を示すことが効果的です。
さらに、BtoBマーケティングでは複雑な購買プロセスを踏まえ、段階ごとに異なるストーリーや訴求ポイントを最適化することも成功の鍵となります。
例えば、認知段階では課題提起を中心にし、検討段階では具体的な解決事例を、意思決定段階ではブランドの信頼性やビジョンを強調するストーリー展開が効果的です。
社内人材を活かしたオウンドチャネルの立ち上げと運用
BtoB企業のデジタルマーケティングにおいて、社内人材を活用したオウンドチャネルの立ち上げと運用は、競争力強化の重要な戦略の一つです。自社の専門知識や経験を持つ社員が発信するコンテンツは、信頼性が高く、顧客や見込み客に対して説得力のある情報提供が可能となります。
オウンドチャネルとは、企業が自ら管理・運営する情報発信の場であり、ウェブサイト、ブログ、SNSアカウントなどが含まれます。
社内人材を活かすことで、外部委託だけでは難しいリアルな業務知識や最新の技術動向をタイムリーに発信できる点が大きなメリットです。
以下の表は、社内人材を活用したオウンドチャネルの主なメリットと運用のポイントをまとめたものです。
|
メリット
|
内容・効果
|
| 専門性の高いコンテンツ提供 | 社員の知見を活かし、業界や製品に関する深い情報を発信。顧客からの信頼獲得につながる |
| 迅速な情報発信 | 市場や技術の変化に即応し、最新トレンドや社内の取り組みをタイムリーに届けられる |
| ブランドイメージの強化 | 企業文化や価値観を反映したコンテンツで、独自のブランドストーリーを構築 |
| コスト効率の良さ | 外部制作に比べてコストを抑えつつ、継続的なコンテンツ発信が可能 |
| 社内コミュニケーションの活性化 | 社員の参加促進により、組織全体の情報共有と一体感が向上 |
オウンドチャネル運用の成功には、明確な戦略策定と社内体制の整備が不可欠です。具体的には、以下のポイントが重要となります。
-
社内人材の役割と責任を明確化し、コンテンツ作成者や編集者、運用管理者の役割分担を行う
-
品質やトーン、情報の正確性を保つため、コンテンツ制作のガイドラインを整備する
-
継続的な情報発信を実現するため、定期的なコンテンツ発信計画を策定する
-
社員間での情報共有や意見交換を活性化し、コンテンツの質向上を図る
-
アクセス解析やフィードバックをもとにコンテンツ戦略をブラッシュアップする
変化の早いデジタルマーケティングは、常にトレンドを追いながら柔軟に対応することが重要
デジタルマーケティングの最新トレンドを取り入れることで、BtoB企業は競争力を維持し、成長することが可能です。生成AIやパーソナライゼーション、ゼロパーティデータの活用が重要で、これにより顧客との関係を強化し、施策の効果を最大化できます。また、データプライバシーを重視した信頼性の高いマーケティングが求められます。
新しい技術やプラットフォームを積極的に採用し、規制環境にも柔軟に対応することで、競争優位を確立できるでしょう。常に最新情報をキャッチし、柔軟に対応することが成功の鍵です。
最終的に、これらのトレンドを効果的に活用することで、持続可能なビジネス成長を実現し、市場での確固たる地位を築くことができるでしょう。
わたしたち電通B2Bイニシアティブは、BtoB事業の成長を加速させるデマンドジェネレーションとブランディングのプロフェッショナルです。
電通グループの強みである広範なネットワークと豊富なデータ資産、そしてBtoBに特化した専門チームの知見を活かし、以下の領域をトータルで支援します。
- 事業戦略の立案
- 顧客体験(CX)の最適化
- マーケティング/営業活動の支援
- DX導入
わたしたちの核にあるのは、広告コミュニケーションで培ってきた「人の心を動かす力」です。この力を活用し、経営・人材・組織・事業といったあらゆるレイヤーにおける課題に向き合いながら、具体的な施策の実行から最終的な成果を分析・改善し続けるためのサイクルの創出まで伴走します。
単なる「施策の提供」にとどまらず、強いブランドづくりや売れる仕組みの構築を通じて、企業の持続的な成長と信頼性の高いパートナーシップの実現を目指します。
デジタル領域における、BtoBに特化した多様なご支援が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。
電通B2Bイニシアティブのソリューション詳細はこちら

PROFILE
B2B Compass編集部