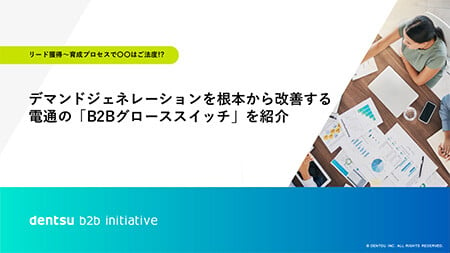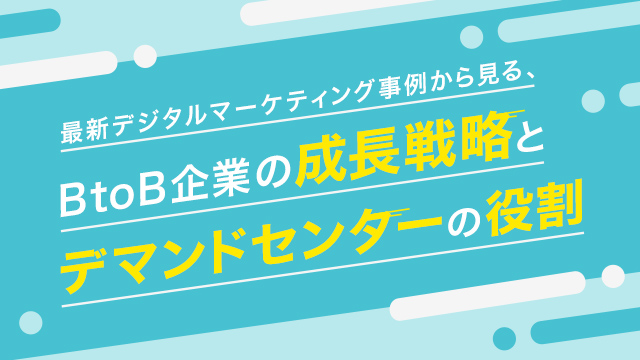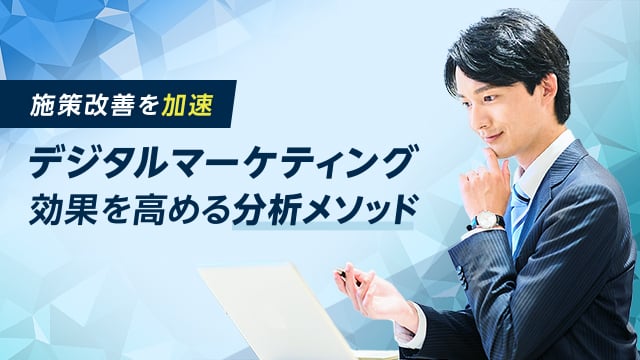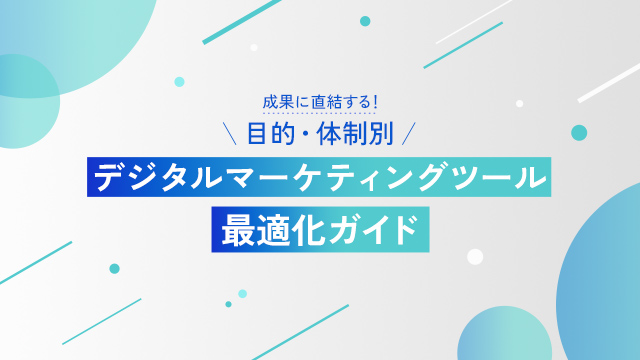急速に変化するデジタルの世界で、どのようにして自社の存在感を高め、競争優位を確保するかは多くの企業が直面する課題です。
そこでデジタルマーケティングの戦略を正しく構築することで、リソースを効果的に活用し、ROIを最大化することが可能となります。
今回は、デジタルマーケティング成功への道筋を描くための具体的な戦略設計プロセスをご紹介します。
INDEX
デジタルマーケティング戦略設計の全体像
急速に進化するデジタル環境において、効果的な戦略立案には、単発的な広告施策ではなく、ビジネス全体の方向性と連動した包括的な設計が不可欠です。
以下に、デジタルマーケティング戦略設計の全体イメージを、おおまかに整理しました。
- 1.ビジョンと方向性を描く
- 2.データ戦略とプライバシー対応を設計する
- 3.顧客理解(顧客インサイト)を深める
- 4.テクノロジースタック(マーテックスタック)を最適化する
- 5.接点と関係性を設計する
- 6.価値伝達の仕組み構築
- 7.成果を測り、磨き続ける
ビジョンと方向性を描く
デジタルマーケティング戦略の成功は、明確な戦略方針の設定から始まります。これは後続の現状分析、ターゲット設定、チャネル選定、コンテンツ設計すべての基盤となる重要なステップです。
戦略方針で定めるべき要素
- 事業目標との連動性
- 売上目標、市場シェア、ブランド認知度など、事業戦略と直結した指標を設定
- デジタル変革の位置づけ
- 既存営業プロセスとの統合度合いと、デジタル施策の役割を明確化
- 投資方針と優先順位
- 限られたリソースをどの領域に集中させるかの基本方針を策定
データ戦略とプライバシー対応を設計する

現代のデジタルマーケティングにおいて、データ活用と個人情報保護の両立は経営レベルの重要課題です。法規制遵守はもちろん、顧客との信頼関係構築の基盤となる戦略的取り組みが求められます。
データ戦略の設計要素
- データガバナンス体制の構築
- 収集・保管・利用に関するルール策定と責任者の明確化
- プライバシーバイデザインの実装
- 個人情報保護法、GDPR等の規制要件を設計段階から組み込み
- ファーストパーティデータの強化
- Cookie規制に対応した自社データ資産の構築と活用基盤の整備
顧客理解を深める
効果的なマーケティング施策の前提となる顧客理解は、表面的な属性データだけでなく、購買動機や意思決定プロセスの深い洞察が必要です。
顧客インサイト獲得のアプローチ
- 行動データと心理データの統合分析
- Webサイト行動ログと顧客インタビューデータの組み合わせ
- カスタマージャーニーの可視化
- 認知から購買後まで、各段階での顧客体験と課題の特定
- ペルソナの精緻化
- 定量・定性データに基づく実践的な顧客像の構築
テクノロジースタック(マーテックスタック)を最適化する
マーケティング効率化と成果最大化には、適切なテクノロジー選定と統合運用が不可欠です。ツールありきではなく、戦略に基づいた最適化が重要です。
マーテックスタック最適化の観点
- データ統合基盤の構築
- CRM、MA、Web解析ツール間のシームレスなデータ連携
- 自動化とパーソナライゼーション
- 顧客行動に応じた適切なタイミングでのコミュニケーション実現
- ROI測定とアトリビューション分析
- 各チャネルの貢献度を正確に把握する測定体制の構築
接点と関係性を設計する
顧客との多様な接点を戦略的に設計し、一貫したブランド体験を提供することで、長期的な関係構築を実現します。
接点設計の重要要素
- オムニチャネル体験の統合
- オンライン・オフライン問わず一貫した顧客体験の提供
- エンゲージメント最適化
- 各チャネルの特性を活かした効果的なコミュニケーション設計
- 関係性の段階的深化
- 認知から顧客化、さらにはアドボケイト化への道筋の設計
価値を伝える仕組みをつくる

商品・サービスの価値を顧客に効果的に伝え、行動変容を促すためのコンテンツとメッセージング戦略を構築します。
価値伝達の設計要素
- バリュープロポジションの明確化
- 競合との差別化要因と顧客ベネフィットの具体的表現
- ストーリーテリング戦略
- 顧客の共感を呼ぶブランドストーリーの構築
- コンテンツマーケティング体制
- 継続的な価値提供を可能にする制作・配信体制の整備
成果を測り、磨き続ける
KPIを設定し、施策の効果を定量的に測定。分析結果に基づき、PDCAサイクルを回して戦略を継続的に改善し、変化する市場や顧客ニーズに対応します。
測定・改善の仕組み
- 多層的KPI設計
- 短期成果と中長期成果を組み合わせた包括的な評価体系
- データドリブンなPDCAサイクル
- 定量分析に基づく迅速な施策改善と最適化
- 組織学習の促進
- 成功・失敗事例の蓄積と組織全体での知見共有
これらのステップは相互に関連し合いながら、デジタルマーケティング戦略の効果的な立案と実行を支えます。
デジタルマーケティングの基本情報はこちらをご参考ください。
【5分でわかる】デジタルマーケティングとは?基本と実施プロセス&手法一覧、成功事例を紹介
デジタルマーケティング戦略設計ステップ
ここでは、上記を踏まえ、よりわかりやすく戦略設計の具体的なステップを解説していきましょう。上記の全体像をよりわかりやすく落とし込むと、大きく以下4つのステップに分類できます。
|
ステップ
|
目的
|
主な作業内容
|
注目ポイント
|
| Step 1:現状分析 | 自社の立ち位置を把握し課題を明確化 | 市場調査、競合分析、顧客データの分析 | 正確なデータ収集と課題の本質的把握 |
| Step 2:ターゲット設定 | 明確なターゲットとペルソナ設計 | 顧客セグメント分析、顧客像設計、購買プロセス設計 | 顧客視点の深掘りとニーズ把握 |
| Step 3:チャネル選定 | 最適な接点選びで効果的なリーチを実現 | チャネルの特性分析、媒体選定、連携プラン作成 | チャネル特性に応じた施策設計 |
| Step 4:コンテンツ設計 | チャネルに適した施策の具体化 | メッセージ戦略、コンテンツ企画、効果測定設計 | 顧客の心に響く価値提供と効果測定 |
デジタルマーケティング戦略Step 1:現状分析
効果的な戦略設計には、正確な現状把握が不可欠です。主観的な判断ではなく、データに基づいた客観的分析により、自社の立ち位置と改善の方向性を明確にします。
現状分析では以下5つの観点から包括的に評価を行います。
- 1. 市場環境とトレンド分析
業界動向、顧客行動の変化、技術進歩を把握し、戦略設計の前提条件を整理 - 2. 競合ベンチマーク分析
競合他社のデジタル施策を体系的に調査し、自社の相対的優位性と課題を特定 - 3. 自社リソース診断
マーケティング体制、予算、人材スキルの現状を評価し、実行可能性を判断 - 4. テクノロジー資産評価
既存システムとデータの活用状況を棚卸しし、効率化の余地を発見 - 5. 顧客データ統合度診断
顧客情報の一元管理レベルを評価し、施策精度向上の基盤を確認
|
分析項目
|
ポイント
|
具体的な方法
|
| 市場環境とトレンド分析 | 業界動向の把握と顧客行動変化を捉える | 業界レポート分析、顧客アンケート、競合動向調査 |
| 競合ベンチマーク分析 | 競合他社との差別化要因の特定 | Webサイト分析、広告調査、サービス比較表作成 |
| 自社リソース診断 | 内部体制と改善余地の評価 | 社内インタビュー、過去実績分析、スキルマップ作成 |
| マーケティング技術基盤評価 | システム連携状況と効率化余地 | 利用ツール一覧作成、データフロー図作成、ROI分析 |
| 顧客データ統合レベルの診断 | 顧客情報の一元管理状況と分断の有無の把握 | データベース構造のレビュー、重複データの検出、統合システムの有無確認 |
これらの分析を通じて得られたインサイトは、次のターゲット設定やチャネル選定の精度向上に直結し、成果を最大化するための戦略基盤を強化します。
デジタルマーケティング戦略Step 2:ターゲット設定と顧客理解

現状分析で得られた知見を基に、効果的にアプローチすべきターゲットを明確に定義します。BtoBマーケティングでは個人ではなく組織全体の意思決定構造を理解することが成功の前提となります。
ターゲット企業の明確化
まず企業レベルでのターゲティングを行います。どのような企業に最も価値を提供できるかを明確に定義します。
設定すべき企業条件は以下です。
- 1. 基本属性
業界、従業員数、売上規模、成長段階、地域などの基本情報 - 2. 抱えている課題
対象企業が抱える具体的な課題と、その課題の緊急度・重要度 - 3. 予算・決裁体制
導入予算の規模と決裁プロセスの複雑度 - 4. 自社の強みが活かせる領域
競合と比較して自社ソリューションが最も効果を発揮できる企業特性
組織内の関係者分析
ターゲット企業内で影響力を持つ関係者を詳細に分析し、それぞれに適したアプローチを設計します。
主要な関係者は以下です。
- 1. 担当者(実際の利用者)
実際にサービスを使用する現場レベルの課題と期待 - 2. 管理職(推進者)
部門の成果向上を求める中間管理職の動機と障壁 - 3. 決裁者(経営層)
最終判断を下す経営層の判断基準と重視するポイント
|
関係者
|
主な関心事
|
効果的なアプローチ
|
| 担当者 | 業務効率化、使いやすさ、操作の簡単さ | 機能デモ、無料体験、導入事例の共有 |
| 管理職 | 部門成果向上、導入の確実性、チーム生産性 | 効果測定資料、導入支援体制、成功事例 |
| 決裁者 | 投資対効果、戦略目標達成、リスク管理 | 経営価値の提案、競合比較、導入保証 |
インテントデータ(購買意向データ)の活用
サードパーティが提供する匿名化された業界全体の行動トレンドデータを活用して、市場の購買意向を把握します。
活用できるインテントデータは以下です。
- 1. 業界全体の検索トレンド
特定のキーワードや製品カテゴリの検索ボリューム変化から市場の関心度を測定 - 2. コンテンツ消費パターン
業界関連コンテンツの閲覧傾向から、どのような課題への関心が高まっているかを把握 - 3. 地域別の行動変化
特定地域での関連情報への関心度から、その地域の市場機会を発見 - 4. 競合関連の検索動向
競合他社名や関連キーワードの検索傾向から、市場の動きを予測
これらのインテントデータを分析することで、「どの業界・地域で購買検討が活発化しているか」を把握し、効率的なターゲティングとタイミングでのアプローチが可能となります。特定企業の行動は分からないものの、市場全体の動向を先読みできる貴重な情報源です。
購買プロセスの整理
BtoB購買は時間をかけた慎重な検討プロセスです。各段階での関係者の心理と必要な情報を整理します。
購買の3段階は以下です。
- 1. 課題認識・情報収集段階
現状の問題を認識し、解決手段を幅広く調査する - 2. 要件整理・比較検討段階
自社要件を明確化し、候補サービスを詳細に比較する - 3. 社内合意・最終決定段階
組織内での承認を得て、導入を正式決定する
各段階で適切な情報提供とコミュニケーションを行うことで、効率的な商談創出が可能となります。
デジタルマーケティング戦略Step 3:チャネル選定

Step2で明確化したターゲットに対して、最も効率的にアプローチできるチャネルの組み合わせを設計します。単一チャネルではなく、購買プロセス全体を通じた一貫した顧客体験の構築が重要です。
BtoB購買プロセスに沿ったチャネル設計
各購買段階で最適なチャネルを選定し、段階的な関係構築を実現します。
購買段階別のチャネル戦略の考え方は以下です。
- 1. 課題認識・情報収集段階
幅広い情報提供により認知拡大と初期関心を獲得 - 2. 要件整理・比較検討段階
詳細情報の提供と個別対応により検討を深化 - 3. 社内合意・最終決定段階
意思決定支援と関係者への働きかけを強化
チャネル別の役割分担
|
チャネル
|
主な役割
|
購買段階での活用
|
BtoB特有の活用ポイント
|
| Webサイト | 情報提供の基盤、信頼性構築 | 全段階で継続活用 | 企業情報、実績、セキュリティ対応の明示 |
| オンラインセミナー | 専門知識の提供、リード獲得 | 課題認識・情報収集段階 | 業界課題の解説、ソリューション紹介 |
| ホワイトペーパー | 詳細情報提供、専門性の証明 | 要件整理・比較検討段階 | 技術仕様、導入手順、ROI試算 |
| 個別商談・デモ | 具体的提案、疑問解決 | 比較検討・最終決定段階 | カスタマイズ提案、導入支援体制 |
| メールマーケティング | 継続的関係維持、情報提供 | 全段階でのフォローアップ | セグメント配信、タイミング最適化 |
| 展示会・イベント | 直接対話、関係構築 | 課題認識・信頼構築段階 | 競合比較、業界ネットワーキング |
チャネル統合とデータ連携
効果的なBtoBマーケティングには、チャネル間の情報連携と一貫したメッセージングが不可欠です。
具体的な統合設計の重要要素は以下となります。
- 1. 顧客データの統合管理
各チャネルでの行動履歴を一元化し、個別の購買進行度を把握 - 2. メッセージの一貫性確保
チャネルが変わっても同じ価値提案と情報レベルを維持 - 3. 営業プロセスとの連携
マーケティングで育成したリードを営業に効率的に引き継ぎ - 4. 効果測定と最適化
チャネル別の貢献度測定と、全体最適に向けた継続改善
この統合的なチャネル設計により、見込み顧客は購買プロセス全体を通じて一貫した体験を得られ、効率的な商談創出が実現します。
デジタルマーケティング戦略Step 4:コンテンツ戦略と制作体制
Step2のターゲット設定とStep3のチャネル選定を基に、効果的なコンテンツ戦略を構築します。BtoBマーケティングでは、複雑な意思決定プロセスを支援する体系的なコンテンツ設計が成功の鍵となります。
購買段階別コンテンツ設計
各購買段階で求められる情報と関係者のニーズに合わせて、戦略的にコンテンツを設計します。
|
購買段階
|
主要な関係者
|
必要なコンテンツ
|
制作のポイント
|
| 課題認識・情報収集 | 担当者・管理職 | 業界動向資料、課題解決事例、入門ガイド | 課題の明確化と解決の方向性を示す |
| 要件整理・比較検討 | 管理職・決裁者 | 機能比較表、ROI試算、導入事例 | 具体的なメリットと導入効果を数値化 |
| 社内合意・最終決定 | 決裁者・関係部署 | 提案書、契約条件、導入計画書 | リスク対策と導入後のサポート体制を明示 |
BtoB特有のコンテンツタイプ
一般的なマーケティングコンテンツとは異なる、BtoB特有のコンテンツ要件を理解した制作が重要です。
重要なコンテンツタイプには以下が挙げられます。
- 1. 技術仕様書・ホワイトペーパー
専門性の証明と詳細情報の提供により信頼性を構築 - 2. 導入事例・成功事例
同業他社の実績により導入後のイメージを具体化 - 3. ROI・効果試算資料
投資対効果を数値で示し、経営判断を支援 - 4. セキュリティ・コンプライアンス資料
企業として必要な安全性と法的要件への対応を証明
継続的制作体制の構築
一時的なコンテンツ制作ではなく、継続的に質の高いコンテンツを制作できる体制を整備します。
体制構築の要素は以下です。
- 1. 役割分担の明確化
企画、制作、校正、公開の責任者と承認プロセスを定義 - 2. 営業との連携強化
現場の声を反映したコンテンツ企画と、営業ツールとしての活用 - 3. 品質管理基準の設定
ブランドガイドライン、表記統一、確認手順の標準化 - 4. 効果測定と改善サイクル
コンテンツ別の効果測定と、データに基づく継続的改善
この体系的なコンテンツ戦略により、見込み顧客の購買プロセス全体を支援し、効率的な商談創出と成約率向上を実現できます。
わたしたち電通B2Bイニシアティブでは、BtoB事業活動全般の戦略立案はもちろんのこと、デジタル領域の知見を活用した具体的な施策の実行から最終的な成果を分析・改善し続けるためのサイクルの創出まで伴走支援が可能です。
支援の詳細については、以下をご覧ください。
デジタルマーケティング戦略は中長期で目指すべきゴールを意識して設計する

BtoBマーケティングでは、複雑な意思決定プロセスと長い検討期間を前提とした戦略設計が必要です。現実的なタイムラインと段階的な目標設定により、継続的な成果創出を実現します。
|
期間
|
主な目標の特徴
|
戦略設計でのポイント
|
| 短期(数週間〜数ヶ月) | システム整備と初期体制構築 | データ基盤の整備、コンテンツ制作体制の確立、営業との連携プロセス構築 |
| 中期(数ヶ月〜1年程度) | 安定的なリード獲得と商談創出 | ターゲット精度の向上、コンテンツ最適化、チャネル効果測定と改善 |
| 長期(1年以上) | 市場ポジション確立と成長基盤構築 | 顧客成功体験の蓄積、ブランド価値向上、持続的成長モデルの確立 |
BtoB特有の時間軸を考慮した戦略設計
BtoBマーケティングでは、一般的なマーケティングとは異なる時間感覚での設計が重要です。
重要な考慮事項
- 1. 検討期間の長さへの対応
平均6-18ヶ月の検討期間を前提とした継続的なコミュニケーション設計 - 2. 複数関係者への段階的アプローチ
担当者→管理職→決裁者の順番での関係構築スケジュール - 3. 営業プロセスとの連動
マーケティング活動と営業活動のタイミング調整と役割分担 - 4. 成果測定の複層化
短期的な活動指標と中長期的な事業指標を組み合わせた評価体系
このような現実的な期間設定と段階的な目標により、BtoBマーケティング戦略は確実な成果創出と持続的な成長を実現できます。
中長期での成果を正確に測るための指標と視点
BtoBデジタルマーケティング戦略において、中長期的な成果を正確に把握するためには、営業成果に直結する指標と、マーケティング効率を示す指標を組み合わせた評価が重要です。
売上だけでなく、営業プロセス全体の効率化と顧客獲得コストの最適化を包括的に測定することで、持続的な成長につなげることが可能となります。
以下は、中長期での成果を測る代表的なKPIとその特徴をまとめた表です。
|
KPIの種類
|
評価対象
|
特徴と活用例
|
| 営業成果指標 | 商談・受注の質と量 | 商談数、受注率、平均案件単価、受注期間など。営業への直接的な貢献度を測定し、ROI算出の基礎データとして活用 |
| マーケティング効率指標 | 投資効果と獲得コスト | CPL(リード獲得単価)、CAC(顧客獲得コスト)、ROAS(広告費用対効果)など。予算配分の最適化と施策の費用対効果を評価 |
| 営業連携指標 | マーケティングと営業の協力度 | MQL→SQL転換率、営業満足度、リードフォロー率など。部門間の連携効率と、リードの質向上を測定 |
| 顧客育成指標 | 見込み顧客の成長度合い | リードスコア向上率、コンテンツ閲覧深度、セミナー参加継続率など。中長期的な関係構築の進捗を評価 |
| 事業貢献指標 | 最終的なビジネス成果 | 売上貢献額、新規顧客数、既存顧客からの紹介数など。デジタルマーケティングの事業への実質的な貢献を測定 |
これらの指標を設定する際のポイントは、自社の事業特性と営業プロセスに合わせてKPIを選定することです。単に数値を追うのではなく、営業チームとの連携強化と顧客獲得効率の向上を目的とし、測定可能で改善につながる指標を明確に設定することが重要です。
また、定期的なモニタリングと分析を行い、得られたデータから改善点を抽出して戦略の最適化に活用することが成果最大化の鍵となります。
BtoBマーケティングでは、短期的な反応よりも中長期的な関係構築を重視し、営業プロセス全体の効率化を通じて持続的な競争優位を築くことが重要です。
中長期でのゴール達成のためのPDCAサイクルと改善アプローチ

BtoBデジタルマーケティング戦略において、PDCAサイクルは営業との連携を前提とした継続的改善の基盤となります。
長期間にわたる複雑な購買プロセスと複数の意思決定者への対応を考慮した、実践的な改善サイクルの構築が成功の鍵です。
|
PDCAフェーズ
|
役割
|
デジタルマーケティングにおける具体的運用ポイント
|
| Plan(計画) | 営業連携を前提とした施策設計 | 営業チームとの合意に基づくKPI設定、ターゲット・コンテンツ・タイミングの最適化、四半期単位でのリソース配分 |
| Do(実行) | 施策実行と営業との情報連携 | MAツールとCRMの完全連携、リアルタイムでのリード情報共有、営業フィードバックの迅速な反映 |
| Check(評価) | 営業成果を含む包括的な効果測定 | 商談転換率・受注率の分析、営業満足度調査、長期的な顧客育成効果の評価 |
| Act(改善) | データに基づく戦略調整と組織改善 | 営業プロセスとの連携改善、コンテンツ・チャネル戦略の見直し、体制・ツール運用の最適化 |
BtoB特有の改善アプローチ
BtoBマーケティングのPDCAサイクルでは、以下の特有の要素を重視した改善アプローチが必要です。
重要な改善ポイントは以下です。
- 1. 営業チームとの密接な連携
週次・月次での営業との振り返り会議により、リードの質と営業プロセスの改善を継続的に実施 - 2. 長期的な視点での効果測定
短期的な反応だけでなく、6-18ヶ月の時間軸での関係構築効果を評価 - 3. 複数関係者への影響度測定
担当者・管理職・決裁者それぞれへのアプローチ効果を個別に分析・改善 - 4. 案件の個別性への対応
標準的な施策に加え、重要案件への個別対応戦略の設計と効果検証 - 5. 営業ツールとしてのコンテンツ活用
マーケティング制作コンテンツの営業現場での活用状況とフィードバック収集
これらのBtoB特有の改善アプローチにより、デジタルマーケティング戦略のPDCAサイクルはより実効性の高いものとなり、営業プロセス全体の効率化と成果最大化に寄与します。
デジタルマーケティング戦略におけるファネルごとの設計&コンテンツの考え方
BtoBデジタルマーケティング戦略におけるファネルの設計は、顧客の複雑な購買プロセスと複数の関係者への対応を深く理解することから始まります。一般的に、ファネルは
- 認知(Awareness)
- 検討(Consideration)
- 購買(Decision)
のプロセスに分けられ、それぞれに対応するコンテンツが必要です。これを
- TOFU(Top of the Funnel)
- MOFU(Middle of the Funnel)
- BOFU(Bottom of the Funnel)
の3段階として捉えることで、効果的なコンテンツ戦略を構築できます。
特にBtoBマーケティングにおいては、購買プロセスがさらに複雑化し、以下の5段階で構成されます。
- 課題認識
現状の問題点を認識し、解決の必要性を感じ始める - 解決策検索
具体的な解決手段を調査し、選択肢を幅広く収集する - ベンダー比較
候補サービスを絞り込み、詳細な比較検討を行う - 内部合意形成
組織内での承認プロセスを経て、関係者の合意を形成する - 最終決定
契約条件を確定し、導入を正式決定する
各段階で異なるコンテンツニーズが発生するため、段階に応じたコンテンツを用意することで、効率的なリード育成と顧客獲得につながります。
さらに、マーケティングと営業の連携を強化するために、ファネルは共通のフレームとして活用されます。これにより、両チームが同じ目標に向かって動くことが可能となり、全体的な効率が向上するのです。
認知段階(TOFU):見込み顧客を増やす

認知段階(TOFU)では、見込み顧客を増やすために、BtoB企業の特性に適したチャネルと指標設計が重要です。幅広いリーチよりも、ターゲット企業への的確なアプローチを重視し、次の段階につながる関係構築を目指します。
認知段階の指標例
- サイト滞在時間・ページ深度:関心度の高さを測定
- 資料読了率・閲覧ページ数:コンテンツへの深い関与を評価
- ウェビナー参加率・質問数:能動的な関心を把握
- 企業ドメインからのアクセス数:ターゲット企業の特定
コンテンツの例として、担当者向けには業界の基礎知識を提供する入門記事や課題整理チェックリスト、最新の業界トレンドを紹介する動画などがあります。
これらは、潜在的な興味を引き出し、自社製品やサービスへの関心を高める役割を果たすものです。
管理職向けには、より具体的な情報を求める傾向があるため、調査レポートやROIを示す業界動向資料を提供することが効果的です。
これにより、管理職が自社のビジネスに対する具体的な価値を見出しやすくなるでしょう。
さらに、決裁者向けには、市場全体を俯瞰するホワイトペーパーや経営視点でのレポートが適しています。これらのコンテンツは、企業全体の戦略に対する理解を深め、意思決定を促進するための材料となります。
認知段階のコンテンツ例
- 担当者向け:課題整理チェックリスト、入門記事、業界トレンド動画
- 管理職向け:調査レポート、ROIを示す業界動向資料
- 決裁者向け:市場全体を俯瞰できるホワイトペーパー、経営視点のレポート
ファネルの最上段に位置するTOFU段階においては、まずは幅広く認知を広げ、次の段階へとつなげる基盤を築くことが鍵。これにより、より多くの見込み顧客を効果的に育成することができます。
検討段階(MOFU):商談につながる有効リードを育成する
検討段階(MOFU)では、商談につながる有効リードとの関係性を深耕することに焦点を当てます。この段階では営業との密接な連携により、質の高いリードの特定と適切なタイミングでの引き継ぎが成功の鍵となります。
検討段階の指標例
- リードスコアリング:行動履歴と企業属性による数値化評価
- MQL(マーケティング承認リード)基準:営業引き継ぎの明確な条件設定
- エンゲージメント深度:複数コンテンツへの継続的な関与
- 検討段階の進行度:課題認識から具体的検討への移行度合い
具体的なコンテンツとして、担当者向けには製品やサービスの具体的な機能紹介やFAQ、導入プロセスの詳細な説明が求められます。これにより、担当者の理解を深め、商談への移行をスムーズにするでしょう。
管理職向けには、コスト削減事例や効率性改善のユースケースを示すことで、導入のメリットを具体的に伝えます。これにより、管理職が組織内での導入推進に向けた強い賛同を得やすくなるはずです。
さらに、決裁者向けには、競合との比較資料や投資対効果の試算、他社の成功事例を提供します。これらの資料は、決裁者が投資の価値を客観的に評価し、最終的な意思決定を下す際の重要な判断材料となるでしょう。
こうしたコンテンツは、リードの質を高めるだけでなく、商談成立の可能性を大きく引き上げます。
検討段階のコンテンツ例
- 担当者向け:具体的な機能紹介、FAQ、導入プロセス説明
- 管理職向け:コスト削減事例、効率性改善のユースケース
- 決裁者向け:競合比較資料、投資対効果の試算、他社の成功事例
購買段階(BOFU):営業アクションと成約率に直結させる
購買段階(BOFU)は、営業アクションと成約率が密接に結びつく重要なフェーズです。この段階では、個別企業のニーズに応じたカスタマイズされたアプローチと、意思決定を支援する具体的な提案が成功の鍵となります。
購買段階の指標例
- SQL(営業承認リード)転換率:商談の質と営業満足度の指標
- 提案書提出率・受注率:営業プロセスの効率性を測定
- 検討期間短縮:意思決定支援の効果を評価
- 平均案件単価向上:質の高い提案による価値向上
営業活動が具体的に顧客の意思決定に影響を与えるため、1to1提案やトライアル、個別デモといったチャネルが効果を発揮します。
担当者向けには、導入手順書や実務メリットを強調したトライアルなど、実際の運用を想定したコンテンツが有効です。管理職には、ROI試算シートや運用後の効果レポートといった、投資対効果を具体的に示す資料が求められます。
決裁者には、戦略的価値を強調したカスタマイズ提案やCxO向けのプレゼン資料が効果的です。
これらのコンテンツは、各階層のニーズに合わせて最適化され、購買意思決定を後押しします。BOFUでは、個別の顧客ニーズに深く入り込み、具体的な提案を通じて、顧客の最終決定をサポートすることが重要です。
購買段階のコンテンツ例
- 担当者向け:導入手順書、実務メリットを強調したトライアル
- 管理職向け:ROI試算シート、運用後の効果レポート
- 決裁者向け:戦略的価値を強調したカスタマイズ提案、CxO向けプレゼン資料
内部合意形成を支援するコンテンツ設計

BtoBのビジネス環境では、製品やサービスの導入を決定する際に、一人の意思決定者ではなく、複数部門の合意形成が必要不可欠です。
各部門が異なる視点や優先事項を持つことから、全体のコンセンサスを得るためには、ターゲットごとに適したコンテンツを提供することが重要です。
全体向けには、導入プロジェクトの成功事例や、リスクとその対応策を明示することで、導入後の安心感を与えます。これは、部門横断的な理解と協力を促進する基盤となるでしょう。
担当者向けには、現場での具体的な活用マニュアルやPoC(概念実証)資料を提供し、実務面での理解を深めることが求められます。これにより、日常業務にどのように適用できるかを明確にでき、現場レベルでの支持を得られるのです。
管理職向けには、部門横断での効率化ストーリーを描き、組織全体のプロセス改善やコスト削減の可能性を示します。これにより、管理職が導入の価値を理解し、部門内での推進役となることを促せるでしょう。
最終的に、決裁者向けには、経営戦略との整合性を示す資料を用意します。これにより、決裁者が組織全体の戦略的ビジョンに対する貢献度を評価し、最終的な判断を下す手助けとなるのです。
内部合意形成のためのコンテンツ例
- 全体向け:導入プロジェクト成功事例、リスクと対応策の明示
- 担当者向け:現場での活用マニュアル、PoC資料
- 管理職向け:部門横断での効率化ストーリー
- 決裁者向け:経営戦略との整合性を示す資料
ファネルを意識した継続的なKPI改善の考え方とアプローチ
デジタルマーケティング戦略における成果最大化には、ファネル全体を通じたKPIの継続的なモニタリングと、購買プロセスに沿ったボトルネックの特定が不可欠です。これにより、各段階での課題を迅速に把握し、効果的な改善策を講じることが可能になります。
ファネルの各段階(認知、検討、購買、リピート)において、主要なKPIを定期的に追跡することで、進捗の遅れや施策の効果不足を早期に検知できます。
特に重要なのは、単に数字の増減を見るだけでなく、顧客の行動や反応の背景を分析し、どのポイントで離脱や停滞が起きているかを明確にすることです。
また、ファネル内の各段階で提供されるコンテンツが、それぞれの役割を持つペルソナ(担当者、管理職、決裁者)に対して適切に刺さっているかを検証することも重要です。
役割別コンテンツの効果を評価することで、ターゲットごとのニーズに即した最適な情報提供が行えているかを把握し、必要に応じてコンテンツの見直しや強化を行うことができます。
|
検証項目
|
ポイント
|
具体的な検証方法
|
| ファネル全体のKPIモニタリング | 主要指標をリアルタイムに追跡し、異常値やトレンドを把握する | BIツールやダッシュボードでデータを可視化し、定期レポートで共有 |
| 購買プロセスのボトルネック特定 | ステージごとの離脱率やコンバージョン率の分析で課題を抽出 | ファネル分析ツールを活用し、段階別のKPIを比較・評価 |
| 役割別コンテンツの効果検証 | 担当者・管理職・決裁者それぞれの反応や成果を個別に評価 | アンケート調査、行動ログ分析、商談データとの連携 |
自社のデジタルマーケティング競争力を高める最適な戦略設計を図ろう
デジタルマーケティング戦略を設計する際には、自社の目標やターゲットオーディエンスをしっかりと把握し、それに基づいたステップを踏むことが重要です。
現状を分析し、適切なターゲット設定からスタートし、最適なチャネルを選び、効果的なコンテンツを設計することで、より多くの見込み顧客にアプローチできます。また、戦略は短期的な成果だけでなく、中長期的な視点での目標設定も必要です。
PDCAサイクルを活用し、常に改善を図ることで、デジタルマーケティング活動の効果を最大化します。次のステップとしては、この記事で紹介した設計のステップを自社の状況に応じて具体的に実行に移してみましょう。
わたしたち電通B2Bイニシアティブは、BtoB事業の成長を加速させるデマンドジェネレーションとブランディングのプロフェッショナルです。
電通グループの強みである広範なネットワークと豊富なデータ資産、そしてBtoBに特化した専門チームの知見を活かし、以下の領域をトータルで支援します。
- 事業戦略の立案
- 顧客体験(CX)の最適化
- マーケティング/営業活動の支援
- DX導入
わたしたちの核にあるのは、広告コミュニケーションで培ってきた「人の心を動かす力」です。この力を活用し、経営・人材・組織・事業といったあらゆるレイヤーにおける課題に向き合いながら、具体的な施策の実行から最終的な成果を分析・改善し続けるためのサイクルの創出まで伴走します。
単なる「施策の提供」にとどまらず、強いブランドづくりや売れる仕組みの構築を通じて、企業の持続的な成長と信頼性の高いパートナーシップの実現を目指します。
デジタル領域における、BtoBに特化した多様なご支援が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。
電通B2Bイニシアティブのソリューション詳細はこちら

PROFILE
B2B Compass編集部