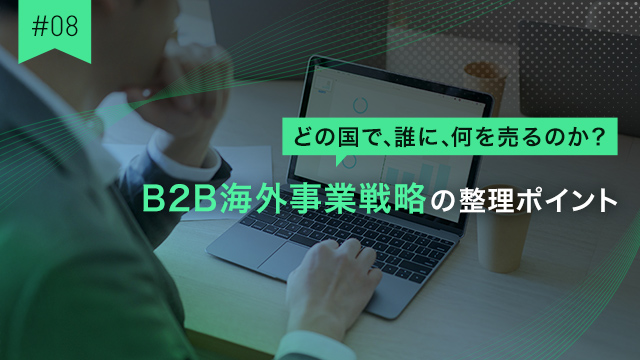現地顧客の「価格感覚」から設計しないと、大きくは勝てない
海外向けの価格を決める場面で、つい頼りたくなるのが「国内価格」を起点にする方法です。国内の販売価格に、海外配送費や関税、通関費用、保険料などを積み上げていけば、いかにも合理的に見える。ところがB2Bでは、「国内価格+海外配送/税関コスト」で輸出価格を作るアプローチは、原則として危ういと言わざるを得ません。
理由は、その計算式の中心にあるのが「日本側の都合」だからです。現地の顧客(購買・技術・経営)がどう評価するか、競合と比べてどのポジションに見えるか、同等スペックの調達価格帯がどこにあるか。そうした視点が抜け落ちたまま価格だけが先に決まると、結果はたいてい中途半端になります。高すぎてRFQに残らないか、安すぎて「品質や供給体制が不安」と見なされるか。あるいは「悪くないが決め手がない」価格帯に置かれて、案件には入るがスケールしない。
海外で本気で成果を狙うなら、出発点を変える必要があります。鍵は、現地の価格受容性からスタートし、そのレンジの中で提供できる価値と提供方法を組み立てることです。この順番を守らない限り、構造的に“大きく勝つ”ことは難しくなります。
INDEX
出発点を変える:「コスト積み上げ」ではなく「現地の価格受容性」
B2Bの「価格受容性」は、単なる支払能力ではありません。顧客が提案を見たときに、「この仕様・この品質保証・この納期・この保守体制なら、その価格でも社内で稟議が通る」と納得できる、という許容レンジのことです。特に重要なのは、単価そのものよりも、顧客の頭の中にある「比較軸」です。
現地の購買担当者は価格地図を持っています。ローカル品のレンジ、欧米ブランドのレンジ、日本ブランドのレンジ。そして多くの場合、比較対象は「製品価格」だけではなく、初期導入費、立ち上げ支援、品質保証、保守、交換部品、教育、停止リスクまで含めた総保有コストに広がります。つまり、見積書が並んだ瞬間に「この提案はこの辺のクラスだ」と分類され、期待値と警戒心が同時にセットされます。
本来は、この地図のどこに自社を置くのかを先に決めるべきです。そのレンジで勝てるように、仕様の切り方、保証条件、サービス範囲、提供スキーム(直販・代理店・現法・保守委託など)を組み合わせていく。ところが現実には、「国内でこの価格だから、海外はコストを上乗せしてこの価格で」と、内側の計算で価格が先に固まってしまうケースが少なくありません。
その結果、日本側から見れば「採算が合う無理のない価格」でも、現地の価格地図の中では“宙に浮いた提案”になります。高いのにプレミアムの根拠が弱い、安いのに体制が疑われる。こうしてボリュームも利益も取り切れない状態に陥ります。
「値下げすれば受注できる」は、B2Bでも危険な思い込み
国内起点の価格が通らないとき、次に出てきやすいのが「では値下げしよう」という判断です。しかしB2Bでは、値下げは受注確率を上げる一方で、別の地雷を踏みやすくなります。特にアジアの一部市場では、安い提案がそのまま「低品質」「供給不安」「保証が弱い」のシグナルとして受け取られることがあります。調達側が怖いのは、購入価格の数%差よりも、停止・不良・クレームの損失だからです。
象徴的なケースとして、ある日系メーカーが部品を海外展開したときの話があります。国内では1個3,000円で売っていた部品を、輸送費や通関費などを積み上げて海外では5,000円で提案したところ、RFQには残るのに決裁に至らない。客先からは明確な拒否理由が出ず、「検討します」で止まる。後で分かったのは、現地では同種部品の調達が「安いレンジ」と「信頼性重視のレンジ」に二極化しており、5,000円はどちらにも刺さらない中途半端な位置だった、ということでした。
そこで発想を変え、製品単価を思い切って上げる代わりに、検査成績書の標準添付、トレーサビリティ、短納期対応、交換条件、立ち上げ時の技術サポートなどをセットにし、「止めないための部品」として再設計して提案した。結果、単価は15,000円相当になりましたが、今度は稟議が通り、採用が進んだ。価格を上げたから売れたのではなく、価格が「位置づけ」と「期待値」を定義し直したのです。
海外で大きく勝つには、「いかに安くするか」ではなく、どの価格レンジに自社を置き、そのレンジで何を約束するかを明確にする必要があります。

クオリティと価格のバランスを、B2Bとして戦略的に割り切る
B2Bの価格戦略で避けたいのが、「高品質だから高くて当然」という内向きの正当化です。もちろん品質は重要です。しかし、それだけでスケールするとは限りません。現地で大きく勝つためには、ときに「クオリティを諦める」判断が必要になることもあります。
誤解してほしくないのは、ここで言う「諦める」とは、悪い製品を売ることではないという点です。そうではなく、現地の一般顧客が認識できない領域の品質に、過剰にコストをかけないという意味です。例えば、現場が本当に求めているのが70点の安定稼働と調達のしやすさだとしたら、70点で十分に勝てる市場がある。そこに80点、90点を目指して「磨き込み」をしてしまうと、コストが膨らみ、結果として価格が上がり、そもそも入札の土俵に乗らなくなります。70点でOKな市場で80〜90点を追うのは、顧客価値ではなく自己満足になりやすいのです。
逆に、90〜100点の品質で勝負するなら、価格も中途半端に抑えるべきではありません。アジアの上位層の企業(大手製造業、インフラ、医療、半導体、データセンターなど)には、日本の平均的な顧客以上の資金力を持つプレイヤーが少なくありません。彼らは「本当に止めない」「監査に耐える」「グローバル標準に合う」ものに対して、相応の対価を支払う合理性があります。90〜100点で提供するなら、思い切って攻めた価格で正面から取りにいく。これもまた、B2Bの勝ち筋です。
要するに、狙うレンジに合わせて、仕様・保証・サービスを意図的に設計し直すこと。価格は最後に付ける数字ではなく、提供価値のパッケージを決める“設計変数”です。
日本の「据え置き感覚」と、アジアの「価格が動き続ける現実」
もう一つ、日本企業が見落としがちなのが「価格改定の頻度」です。インフレ率が低い日本では、価格を数年間変えないのは珍しくありません。しかしアジアの多くの市場では、物価・賃金・物流費・家賃が毎年のように変動します。そうした環境では、価格の見直しは例外ではなく日常です。
現地のローカル企業や欧米企業は、インフレやコスト上昇を前提に価格改定を織り込みながら、契約条件や値上げの説明ロジックまで含めて運用しています。一方で日系企業は「一度決めた価格を変えにくい」慣性が強く、据え置きを続けた結果、実質的に値下げをしているのと同じ状態になりがちです。B2Bほど、これが利益に直撃します。

円安と「円建て卸価格」が生む買い叩き
そこに近年の円安が重なります。輸出時の卸売価格を円建てで固定していると、現地側から見た仕入れ価格は自国通貨換算でどんどん下がっていく。販売価格を大きく変えなくても、現地パートナー(代理店・インポーター)のマージンが自然に厚くなる一方、日本側の収益は薄くなる。極端な場合、日本側だけが苦しいのに現地側は潤う、という構図が生まれます。
さらに、「円安だからもっと下げられるはずだ」と追加の値下げを要求されることもあります。こうなると据え置きは美徳ではなく、買い叩かれやすい状態を固定しているのと同じです。インフレと円安が同時に進む環境では、「価格を変えない」こと自体がリスクになります。
定常的に価格を見直すスキームを作る
では何をすべきか。答えはシンプルで、価格の見直しを「仕組み」にすることです。値上げを担当者の胆力と交渉力に依存させるのではなく、ルールとして運用する。
例えば、インフレ率や主要コストが一定以上上昇したら再検討する、為替が想定レートから一定幅乖離したら条件を協議する、年に一度は主要国の競合価格と価格受容レンジを棚卸しする、といったトリガーを先に決めておきます。そうしておけば、価格改定は「担当者の勇気」ではなく、事前に決めたルールに沿って淡々と実行するプロセスになります。
あわせて、現地の顧客にとって価格が「高いが採用する理由がある」になっているのか、「安いが不安」になっていないか。代理店だけが過度に利益を得ていないか。自社の粗利率が時間とともにどう変化しているか。こうした観点で定期的に点検することで、価格は「決めたら終わり」ではなく「動かし続けるもの」になります。
B2Bの勝てる価格は、偶然ではなく設計で生まれる
最後に強調したいのは、海外のB2B価格は「決め方」ではなく「運用の仕組み」で勝敗がつくという点です。
現地の価格受容レンジを起点に、狙うレンジを決め、そのレンジで勝てる仕様・保証・サービスをパッケージとして設計する。そして、インフレと為替の変動を前提に、価格を定常的に見直すトリガーと手順を持つ。これが揃って初めて、価格は「交渉の結果」ではなく「戦略の武器」になります。
値下げで案件を拾いにいくのか、70点の仕様でボリュームを取りにいくのか、90〜100点で上位層を正面から取りにいくのか。選ぶべきは「安い/高い」ではなく、勝てるレンジに自社を置く意思です。B2Bで大きく勝つ価格は、偶然ではなく、設計と運用で作られます。

PROFILE
B2B Compass編集部